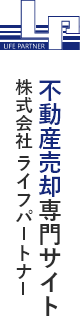- TOP
- お知らせ・コラム一覧
- コラム
- 山形市の不動産相続で気をつけたい固定資産税の落とし穴とは?
山形市の不動産相続で気をつけたい固定資産税の落とし穴とは?

1. 山形市で不動産を相続したらまず確認したいこと
不動産を相続するというのは、一見「もらえてラッキー」と思われがちですが、実は思わぬトラブルや税金の負担が発生する可能性があります。特に山形市のように、空き家の増加が社会問題となっている地域では、不動産の扱いを誤ると固定資産税をはじめとする維持費が重くのしかかってきます。
相続開始後に必要な基本的なステップとは?
まず、「相続」は被相続人(亡くなった方)が亡くなった瞬間から始まります。最初にすべきことは「誰が何を相続するか」を確認することです。遺言書がある場合はその内容を尊重し、なければ法定相続人で分割協議を行う必要があります。
山形市の場合、不動産が中心市街地なのか郊外なのかで評価額や今後の活用方針が大きく異なります。資産価値の見極めも重要です。
固定資産税の負担者は誰?法的なポイント
相続が発生すると、名義変更の有無にかかわらず、1月1日時点で不動産を保有している人に固定資産税の納税義務が発生します。
たとえば、名義が亡くなった人のままになっていても、実際に使っている相続人や代表者に通知が来るケースがあります。これは「現実的に使用・管理している者」が納税義務者とされやすいためです。
したがって、誰が支払うか曖昧なままだと、後々トラブルになりやすく注意が必要です。
相続放棄した場合、税金の支払い義務はどうなる?
相続放棄をすると、法律上は最初から相続人でなかったことになります。そのため、放棄した人に固定資産税の支払い義務は原則としてありません。
ただし、放棄の手続きが遅れたり、市町村に通知しないまま納税通知書が届いた場合、支払いを求められることもあります。放棄する場合は、速やかに山形家庭裁判所での手続きと、市役所への届出を済ませておくことが大切です。
まとめ:まずは「誰が相続するか」「登記をどうするか」
山形市で不動産を相続した場合、相続登記(名義変更)を行うことで法的に所有者が確定します。この登記が済んでいないと、売却・活用・贈与などもできませんし、固定資産税の負担者も曖昧になります。
また、近年では2024年から相続登記の義務化(罰則あり)がスタートしました。これは山形市でも例外ではありません。まずは、相続の基本的な流れと手続きを理解し、税負担や名義の管理に備えることが大切です。
2. 固定資産税とは?山形市の場合の仕組みと特徴
固定資産税は、土地や建物などの「固定資産」に対して市区町村が課す税金です。山形市では、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が課税対象になります。
税額の通知は通常4月〜6月頃に送付され、年4回(6月・9月・12月・翌年2月)の分割納付が可能です。一括で納めることもできます。納付書は山形市役所から郵送されますので、ポストに注意しておきましょう。
山形市における評価基準と他都市との違い

固定資産税の金額は、固定資産税評価額 × 1.4%で計算されます。この評価額は、土地や建物の所在地や大きさ、構造、築年数などをもとに、市が独自に算出するものです。
山形市の場合、都市部と比べて評価額がやや低めに抑えられる傾向にありますが、空き家が多い地域では評価額が変わりにくく、「使っていないのに税金が高い」というケースも見られます。こうした場合には、特例措置の申請や用途変更などを検討することも選択肢になります。
山形市の「都市計画税」も忘れずにチェック
固定資産税と一緒に課されることが多いのが「都市計画税」です。これは都市計画区域内にある不動産にかかるもので、山形市でも市街化区域に該当するエリアの不動産にはこの税が加算されます。
税率は原則として0.3%(評価額×0.3%)で、固定資産税と合算して納付書が届きます。郊外や農地など、市街化調整区域の物件には課税されないこともあるため、対象となるかを市役所で確認しておくと安心です。
まとめ
固定資産税は「所有しているだけでかかる税金」であり、住んでいなくても納税義務は発生します。山形市では評価額や都市計画税の有無など、地域特有のルールもあるため、早めに確認して適切に対応しましょう。
次は、「納税通知書はいつ届く?名義変更との関係」についてご案内します。不動産の相続後、誰にいつ税金の連絡が来るのか気になる方は、ぜひ続きをご覧ください。
3. 納税通知書はいつ届く?名義変更との関係
「相続してからずっと放置していたら、突然税金の通知が来た!」という相談をよく受けます。固定資産税の納税通知書は、誰に・いつ・どうやって届くのかを知っておかないと、思わぬトラブルにつながります。ここでは山形市での実情もふまえて、名義変更と税金の関係をやさしく整理してみましょう。
通知書は「誰に」「いつ」届くのか?
山形市では、毎年4月中旬〜5月上旬ごろに、固定資産税・都市計画税の納税通知書が郵送されます。この通知書は、1月1日時点で登記簿上の「所有者」とされている人宛てに送付される仕組みになっています。
ただし、相続発生後に登記変更をしていない場合、故人の名前のまま通知書が届くことがあります。その場合、家族の中で誰が納税すべきか分からず、混乱の元になります。
前所有者のまま届いた場合の対応方法
もしも亡くなった方の名義で納税通知書が届いた場合でも、放置はNGです。通知書が届いたということは、税金が発生しているということなので、相続人の代表者がまず対応する必要があります。
山形市では、相続人代表者が「代表納税義務者申告書」を提出することで、次年度以降はその人宛てに通知が届くように変更できます。なお、この申告書は市のホームページや資産税課の窓口で入手可能です。
相続登記をしないとどうなる?ペナルティはある?
2024年4月から、相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される制度が始まりました。これにより、不動産の名義変更を放置することが大きなリスクになっています。
名義変更をしないままでは、売却もできず、固定資産税の通知が毎年故人宛に届き続けます。家族が知らずに未納状態になると、延滞金が加算される場合もあります。また、登記が終わっていないと、相続人の中で誰が責任を持つか不明確になり、家族間のトラブルにもつながります。
まとめ
納税通知書は1月1日時点の登記上の所有者に届くため、相続が発生したらできるだけ早めに登記を済ませることが重要です。また、山形市に提出する「代表者申告書」も活用して、誰が責任を持って納税するのかを明確にしておくと安心です。
次章では、「山形市における固定資産税の評価額の決まり方」について詳しく解説します。自分の相続した不動産がなぜその金額になるのか、気になる方はぜひご覧ください。
4. 山形市における固定資産税の評価額の決まり方
固定資産税の金額は「市が決める評価額」によって決まります。でも、「うちの家、そんなに価値があるの?」「なんでこんな金額になるの?」と疑問に思う方も多いですよね。ここでは、山形市での固定資産税評価額の仕組みと、その計算に使われる「路線価」や「倍率表」について、やさしく解説します。
評価額の根拠「固定資産税評価額」とは?
固定資産税の計算に使われる評価額は、「固定資産税評価額」と呼ばれます。これは、不動産の時価(実際に売れる価格)とは異なり、市町村が独自に算出する「課税のための基準価格」です。
山形市では、土地・建物ごとに評価額が設定されており、3年ごとに見直されます。たとえば、2024年が評価替えの年であれば、その時点での市内の地価や建物の劣化状況などが反映されます。評価額が高いほど税金も高くなるため、「どうしてこの金額なのか」を確認しておくことが大切です。
山形市が使う「路線価」や「倍率表」の活用法
土地の評価額は、主に「路線価方式」と「倍率方式」で決められます。山形市内の中心部(七日町・十日町・本町など)では、主要道路に面した土地には「路線価」が設定されています。これは、道路ごとに1㎡あたりの価格が定められており、それをもとに税額が決まります。
一方で、郊外や農地などでは「倍率方式」が採用されます。これは、土地の公的価格に一定の倍率(たとえば0.7倍〜1.2倍など)をかけて評価額を出す方法です。自分の土地がどちらに該当するかは、市役所の資産税課で確認できます。
築年数・地形・用途による評価の違い
建物の評価額は、「再建築価格 × 経年減点補正率」で算出されます。つまり、新築時の価値から年数を経るごとに評価額が下がっていく仕組みです。
たとえば、築30年以上の住宅であれば、評価額が大きく下がり、固定資産税も安くなる傾向にあります。ただし、物置や車庫、増改築した部分は別途評価される場合があるので注意が必要です。
また、同じ広さの土地でも、がけ地や不整形地(変わった形の土地)は評価が低めに、商業地や駅近など利便性の高い場所は高くなります。
まとめ
山形市の固定資産税は、「市が決める評価額」によって大きく左右されます。路線価や倍率表、建物の築年数などが関係しており、必ずしも「実際の売買価格」とは一致しません。評価額に納得がいかない場合や疑問がある場合は、「評価額の縦覧制度(毎年4月上旬〜5月上旬)」を利用して、市役所で他の不動産と比較することもできます。
次章では、「相続人が複数いる場合の固定資産税の取り扱い」についてご紹介します。ご兄弟や親族で相続するケースが多い中、トラブルを防ぐための知識をお伝えします。
5. 相続人が複数いる場合の固定資産税の取り扱い
不動産の相続では、ご家族や兄弟姉妹など複数人で相続するケースがほとんどです。ところが、この場合、固定資産税の請求や支払いを「誰がするのか」が曖昧なままだと、税金未納や相続トラブルの原因になります。ここでは、相続人が複数いるときの固定資産税の取り扱いについて、ポイントを解説します。
固定資産税の納税義務は全員?代表者?
相続登記が完了しておらず、登記簿の所有者が被相続人のままの場合でも、相続人が実質的に不動産を所有しているとみなされ、納税の義務が生じます。
固定資産税の納付書は、山形市の場合、相続人の中から1人の「代表者」宛てに送付されるのが基本です。ただし、これは「その人が全額支払うべき」という意味ではなく、他の相続人も含めた連帯責任が発生することになります。
相続人同士でトラブルを防ぐ分担の決め方
「支払いは兄が全部払ってるけど、私には関係ない」
このような曖昧な状態は危険です。口約束ではなく、誰がいくら負担するのか、文書で決めておくことが大切です。
特に相続財産に他の資産(預金など)がある場合は、不動産の維持費を含めた「トータルでの相続分配」を考える必要があります。固定資産税は毎年発生するため、一時的な精算では済まない点にも注意が必要です。
また、「共有名義」のままにしておくと、今後の売却や再相続の際に話し合いがまとまらず動かせなくなるケースも多いため、将来的なリスクも考慮しておきましょう。
未分割時の納税処理と市役所への申請方法
遺産分割協議がまとまらず、まだ名義変更できていない「未分割」の状態でも、固定資産税は請求されます。この場合、山形市では「相続人代表者申告書」を提出することで、1人の代表者宛てに納税通知書を集約できます。
申請書は市役所資産税課で取得でき、郵送・窓口で提出が可能です。代表者は納税の窓口になりますが、他の相続人と協力して費用を分担することが大前提です。
6. 山形市で利用できる固定資産税の減免制度
「誰も住んでいない家に毎年高い固定資産税がかかって困っている…」という声は、山形市でも少なくありません。特に相続で取得した不動産は、自分では使わないけれど手放すのも難しいというケースが多く、何とか税負担を軽減したいというニーズが高まっています。そこで今回は、山形市で利用できる主な固定資産税の減免制度や特例について、わかりやすく解説します。
山形市特有の住宅用地特例の内容
一方、適切に管理されている住宅や、その敷地については、「住宅用地特例」が適用され、200㎡までの部分は評価額の6分の1に軽減されます。
これは山形市でも全国と同じように運用されており、戸建て住宅が主流の地域では非常に大きな効果があります。たとえば、更地にするとこの軽減措置が使えなくなり、かえって税額が高くなるケースもあるため注意が必要です。空き家でも「居住用家屋」として形が保たれていれば、この特例は引き続き使える可能性があります。
地元限定!申請しないと損する控除制度
山形市では、所得が一定額以下の世帯に対して「減免申請制度」があります。これは、生活保護受給者や収入が激減した高齢者世帯などが対象で、所定の書類を提出することで税額の一部または全額が減免される場合があります。
また、障がい者のいる世帯や災害による被災者など、個別事情に応じた軽減措置も用意されています。これらは申請しないと適用されませんので、該当しそうな方は必ず市役所に相談してみましょう。
まとめ
固定資産税の減免制度は、「何も知らないと損をする」ことが多い分野です。山形市でも、空き家対策、住宅用地特例、所得による減免など、条件さえ満たせば大きな軽減効果が期待できる制度が整っています。
「この家をどうしたらいいのか分からない…」という場合でも、税金のことを整理することで、方向性が見えてくることもあります。不動産相続でお悩みの方はライフパートナーにご相談ください。
7. 相続不動産を活用する場合の節税のヒント
相続した不動産、空き家のままにしていませんか? ただ所有しているだけでも、毎年かかる固定資産税は決して安くありません。山形市のように空き家が増えている地域では、「使っていないのに税金だけがかかる」という負担に悩む方が多くいらっしゃいます。
そんなときは、相続した不動産をうまく活用して節税する方法を検討してみましょう。
賃貸・売却・駐車場経営…固定資産税がどう変わる?
相続した物件を賃貸に出した場合、住宅用地としての特例(200㎡まで評価額1/6)を継続して適用できます。たとえ自分が住んでいなくても、人が住んでいれば「住宅」として扱われ、税金の軽減対象になるのです。
また、土地が広い場合は、一部を月極駐車場や資材置き場として貸すことで固定資産税の一部を賄うことも可能です。実際に、山形市内でも空き地を活用した「貸し駐車場」で年数十万円の収入を得ている事例があります。
逆に、建物を解体して更地にしてしまうと、住宅用地特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。維持費を抑えるつもりが、逆に高くつくケースもあるので注意が必要です。
収益化で節税する!山形市で実現できる活用例
山形市では、以下のような活用方法で実際に節税効果が出ている事例があります。こうした小さな活用でも、「何もしない」よりは収支バランスが良くなり、かつ節税にもつながります。
古民家をリフォームして民泊に活用
地元観光との連携で補助金を活用しつつ固定資産税を経費として計上。
空き家を「お試し住宅」として地域に貸し出す
住宅として使うことで税制優遇を維持。
相続した宅地の一部を家庭菜園付き月貸し用地に転用
非住宅用地としても活用しながら一部賃貸収入を確保。
相続した土地を放置するリスクと税負担

何もせずに空き家や土地をそのまま放置しておくと、固定資産税の負担は年々のしかかってきます。それに加えて、倒壊リスクや景観悪化によって行政からの指導や、住宅用地特例の解除といったペナルティも起こり得ます。
また、2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、使わない土地を国に返す制度ですが、条件が厳しく、実質的には利用しづらいという声も多いです。やはり、できるだけ自分で活用法を探すのが現実的といえるでしょう。
まとめ
相続不動産を有効活用することで、固定資産税の負担を軽くするだけでなく、将来的な資産形成にもつなげられます。山形市では、地域特性に合わせた柔軟な不動産活用が可能です。
「使わない=負担」ではなく、「使う=活かす」方向に目を向けてみましょう。地元の不動産会社や税理士、行政窓口に相談すれば、無理のない活用法がきっと見つかるはずです。
8. まとめ:山形市で不動産相続するなら事前準備と地元制度の理解がカギ
不動産を相続するというのは、一生に何度もあることではありません。だからこそ、いざその場面に直面したときに「知らなかった」「もっと早く調べておけばよかった」と後悔される方も多いのが実情です。特に、山形市のような地域では、空き家の増加や人口減少の影響から、不動産を「持ち続けること自体がリスク」になりかねません。
まずは「名義変更」「税制度」「減免制度」を理解
相続が発生したら、まず確認すべきは「誰が何を相続するのか」、そして「名義変更(相続登記)をどう進めるか」です。2024年からは相続登記が義務化され、登記しないまま放置すると10万円以下の過料が課される可能性もあります。
次に重要なのが、固定資産税をはじめとする税制度の理解です。ただ所有しているだけで課税される固定資産税は、放置していると毎年支払いが必要になります。しかし、住宅用地特例や減免制度を正しく使えば、大きく税額を抑えることも可能です。
山形市では、収入状況に応じた減免申請や、空き家対策を目的とした軽減措置なども設けられていますので、早めに確認しておくと安心です。
山形市の制度を活用して出費を最小限に
山形市は空き家問題に対して積極的な取り組みを進めている自治体の一つです。たとえば、「空き家バンク」への登録や「リフォーム助成制度」など、地域資源を活かした不動産活用の支援も受けられる可能性があります。
また、固定資産税の負担を軽くするために、「人が住んでいる状態を保つ」「賃貸や駐車場として収益化する」「特例制度を活用する」など、具体的な節税対策も選択肢に入れてみましょう。
専門家への相談でトラブルを回避
相続や税金、登記の手続きには専門的な知識が必要な場面も多くあります。「この判断で合っているのか不安」「何から始めたらいいか分からない」というときは、ライフパートナーにご相談ください。創業以来、私たちはお客様からの信頼を第一にきめ細やかなサポートに努めてまいりました。弁護士や司法書士などの専門家とも連携し、相続や税金に関するご相談にも対応いたします。これからも豊富な経験と実績に基づき、お客様にご安心いただけるサポートを実現していきます。
最後に:不動産は“資産”にも“負債”にもなる
相続した不動産は、使い方次第で資産にもなりますが、放置すれば税金や管理の負担が続く“負債”にもなり得ます。
だからこそ、「情報を知っているかどうか」が未来を大きく左右します。
このガイド記事を通して、少しでも山形市で不動産を相続された方の不安を和らげ、適切な対応のヒントになれば幸いです。ぜひ一歩踏み出し、ご家族や専門家と一緒に、大切な不動産の未来を考えてみてください。
Access
株式会社 ライフパートナー
【住所】〒990-2443 山形県山形市南三番町11-25
【電話番号】 023-632-9180
【宅地建物取引業 登録番号】 山形県知事 (4) 第2262号
【加盟団体】
(公社)山形県宅地建物取引業協会
東北地区不動産公正取引協議会加盟